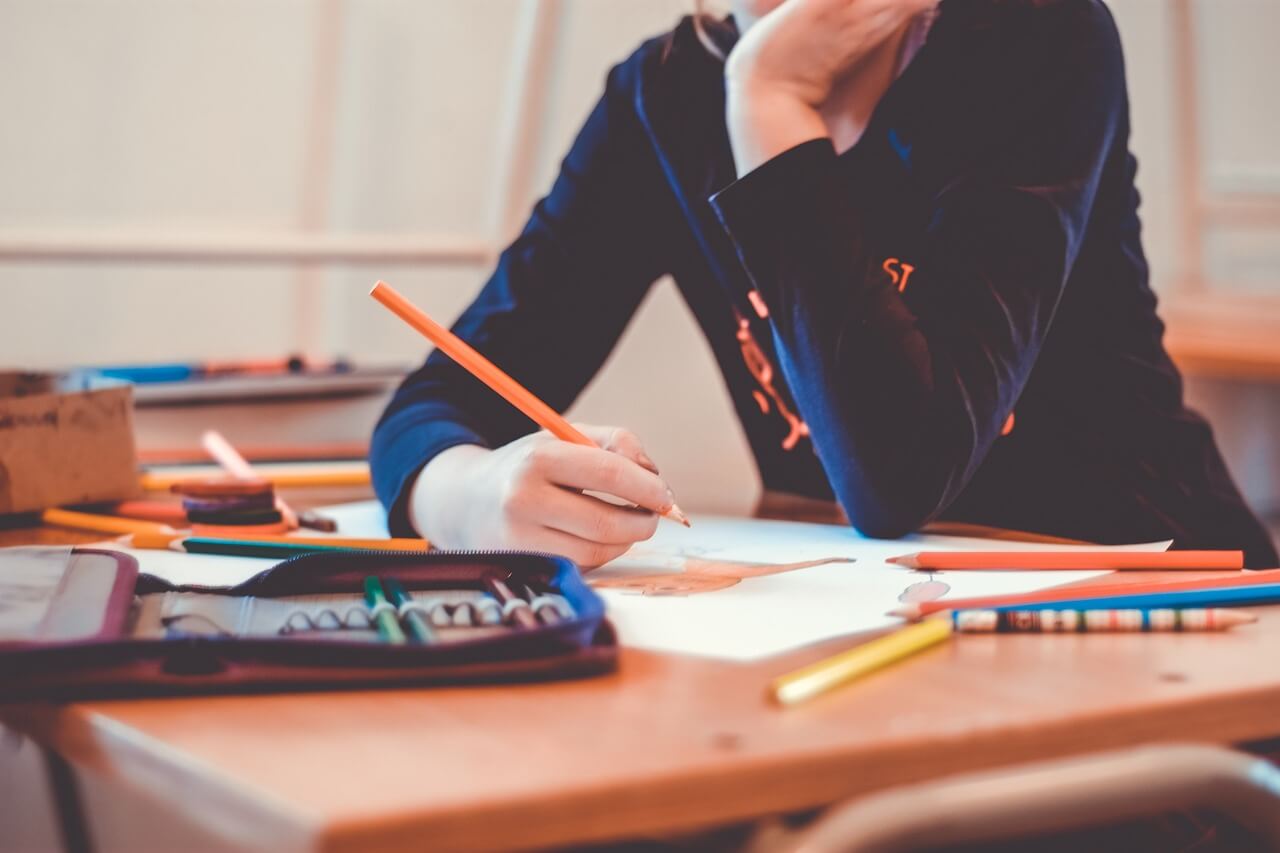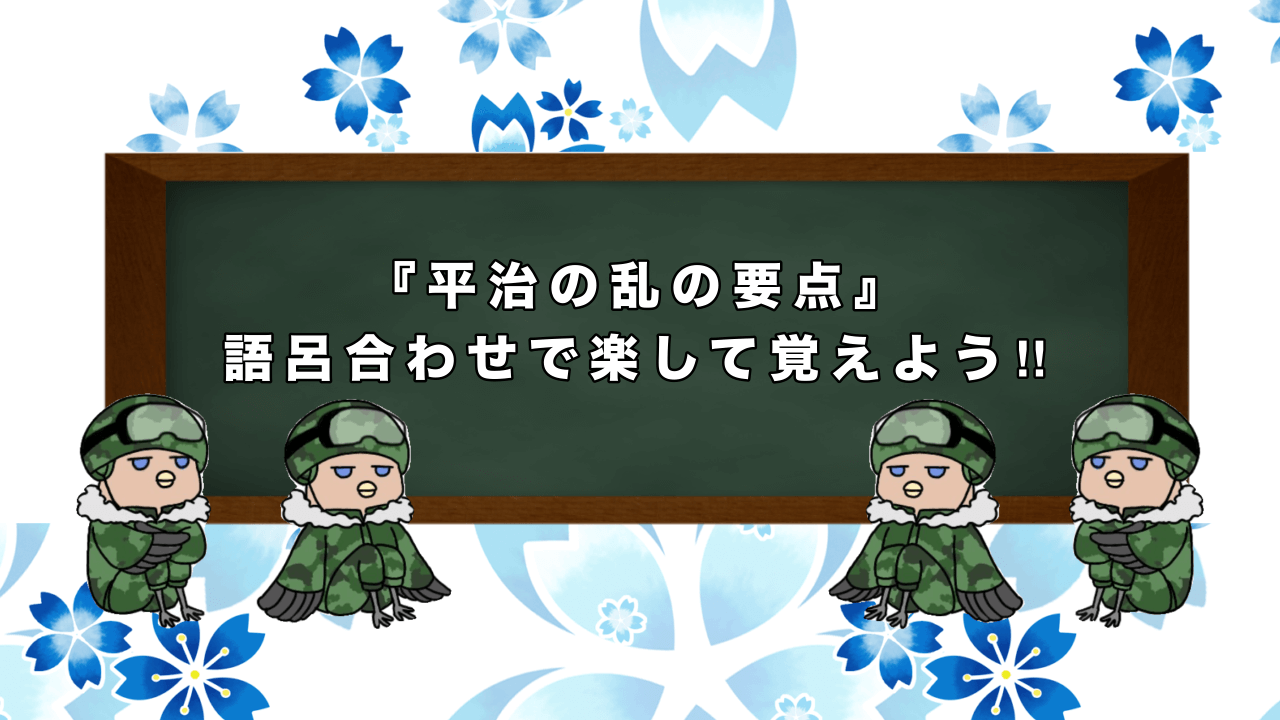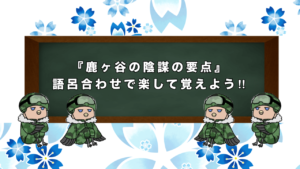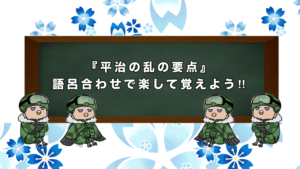バルコニー
バルコニーどうも、バルコニーと申します。
このページでは高校日本史における
治承・寿永の乱(源平の争乱) について
わかりやすく・見やすく・覚えやすく
触れていきます!
平家滅亡に至るまで、様々な出来事が立て続けに起こります。そのため
出来事の順番が分からなくなる。
覚える量が多すぎて覚えきれない。
上記のような状況に陥ってしまう方、
いると思います。
しかし、安心してください。
このブログでは、私が予備校時代に日本史の点数を爆増させた覚え方や語呂合わせを記載しています!!
効率の良い語呂合わせ&覚え方を知りたい方はぜひ参考にしてください!!
便利な語呂合わせだけを知りたい方は、目次から直接「便利な語呂合わせ ~」に飛んでください!!
治承・寿永の乱(源平の争乱)のザックリ解説



まずは「治承・寿永の乱」について
ザックリ見ていこう!!
治承寿永の乱
1180年から1185年にかけて続いた出来事・大乱戦。
この間に、平家の衰退と源氏の躍進が繰り広げられる。
1180年
安徳天皇(高倉天皇と清盛の娘の子)が即位する
1180年
後白河上皇(法皇)の子 以仁王 が平氏追討の命令を出す
1180年 平氏 福原京へ遷都
(半年ほどで平安京へ戻る)
1180年
源(木曽) 義仲 が挙兵する
1180年 南都焼き討ち
(興福寺などの寺社に平重衡が放火する)
1181年 平清盛 死亡
1183年 平家の都落ち
1183年 木曽義仲の都入り
1183年 寿永二年十月宣旨
1184年 宇治川の戦い
木曽義仲vs源義経 木曽義仲 敗死
1184年 一之谷の戦い
1184年 屋島の戦い
1185年 壇ノ浦の戦い
平氏滅亡 安徳天皇入水



こうしてみると、1180年に立て続けに出来事が起こっているね。
治承・寿永の乱 解説①
安徳天皇の即位(1180年)
1180年、安徳天皇が即位しました。
と言っても、穏やかに即位したわけではなく、
平清盛が強引に即位させたものでした。



安徳天皇は、高倉天皇と清盛の娘である徳子の子ども。つまり、清盛の孫だったね!!
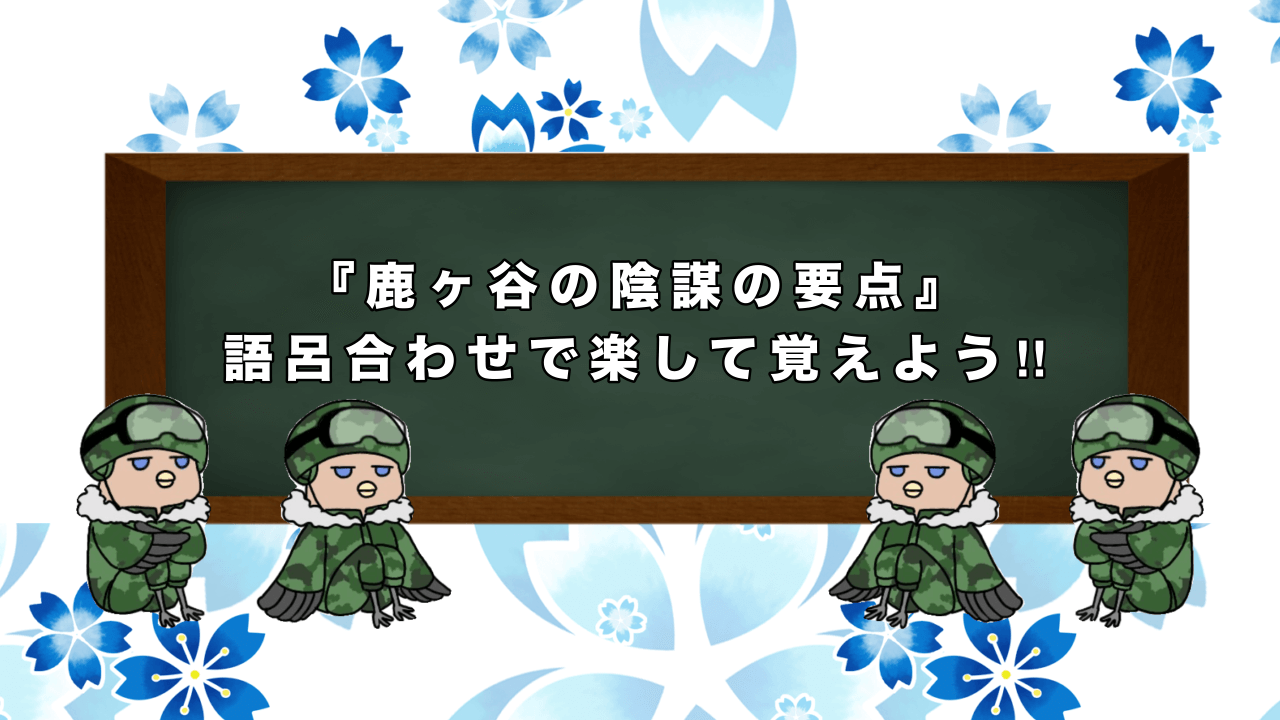
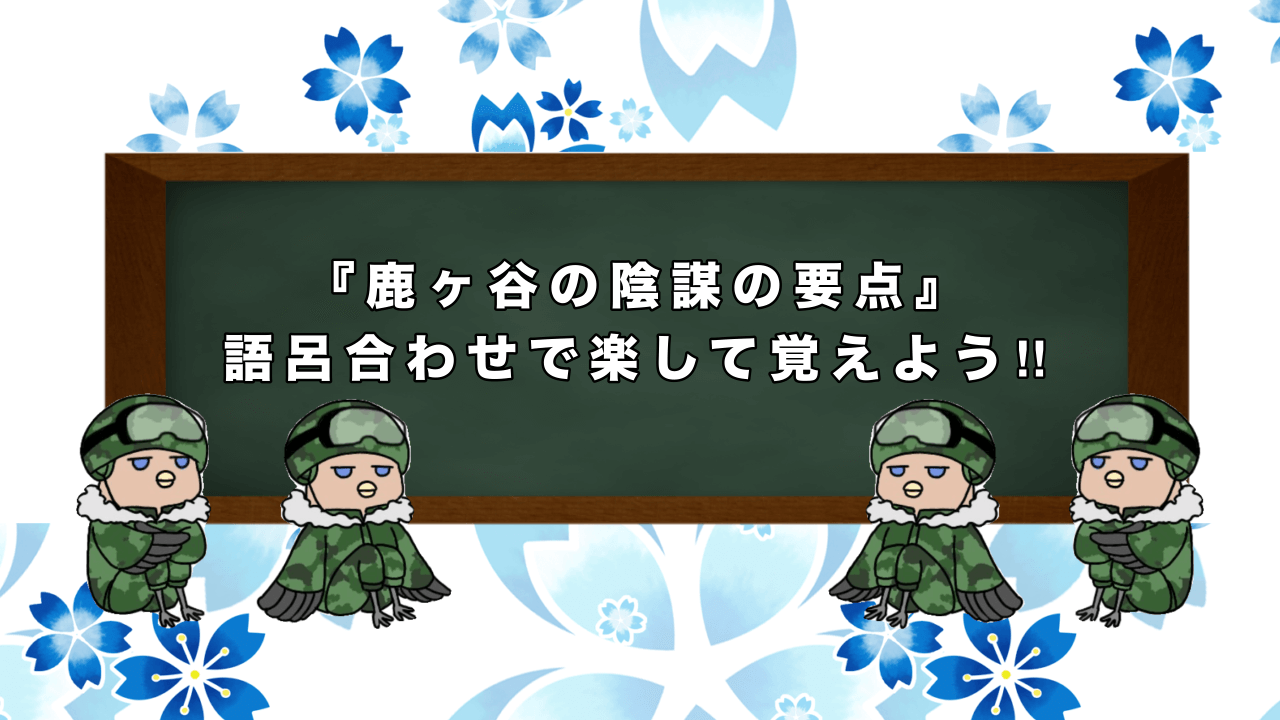
この時、安徳天皇はとても幼く、とても政治をできる状態ではありません。
当然、政治の実権を握るのは平清盛。幼い天皇の補佐という名目で政治の実権を握ります。
無理やり決めた安徳天皇の即位。
しかし、権力・財力・武力そろった平清盛と平氏に、不満を言える者はいません。
しかし、不満は募れば、当然爆発する。
平氏は多くの人間を敵に回してしまうことになります。
治承・寿永の乱 解説②
以仁王の令旨(1180年)
以仁王 は、安徳天皇の即位によって出世の道を絶たれた挙句、自分の荘園の一部を平氏に没収されています。
平氏に対して恨みを抱えている時、源 頼政 が彼に『平氏討伐の話』を持ちかけることで、事態が動き始めます。



源頼政は、保元の乱・平治の乱 ともに勝者側についているよ!!
平治の乱では、源義朝が処刑され、義朝の流れを汲む源氏は没落してしまいました。
しかし、源頼政は最終的に平家側についたため、軍事貴族の地位を維持し続けることができました。
平家政権の中でも、着々と出世していった源頼政ですが、以仁王とともに反平氏の立場となります。
源頼政と以仁王は、都から平家の兵が出払った隙をついて都を占拠する作戦を立案。
諸国の源氏勢力と大寺社に平家追討の挙兵を勧める令旨を下しました。
ところが、平氏追討の情報が清盛の耳に届き、即刻対応。源頼政と以仁王は、逆に追討されてしまいます。



途中までは順調に進んでいたんだけどね……。
劣勢になり、死を悟った源頼政は自害。以仁王も命を落とすことになり 以仁王の令旨 は失敗に終わります。
しかし、亡き以仁王の令旨は各地の源氏たちへと伝わり、確実に平氏を追い詰めていきます。
治承・寿永の乱 解説③
福原京遷都失敗(1180年)
平氏討伐の動きが活発化する中、清盛は、平安京から 福原京 への遷都を実行しようとします。



平安京がある京都から、大輪田泊(現在の兵庫県付近)までのお引越し。
移動費、土地の整備、建築と大きな労力とお金が必要だよ!!
しかし、急すぎる遷都の開始と周囲からの反対もあり、わずか半年で平安京に戻ることになります。



長い平安京の歴史の中で、唯一都が平安京から離れた半年間だったよ!!
治承・寿永の乱 解説④
木曽義仲の挙兵(1180年)
以仁王の呼びかけに応じ、各地の源氏が平氏討伐のために動き出します。木曽義仲もその一人です。



木曽義仲も源氏の家系。
幼少期に信濃国木曽谷(現在の長野県)で暮らしていたことから、木曽を名のるようになったんだ。
平家に不満を持つ人々を味方とし、着実に力を蓄え、平家に連戦連勝。



この功績を認められ、木曽義仲は都入りすることになるよ!!
後に歴史を大きく動かす 源頼朝 も令旨を受け取り挙兵していますが、義仲と頼朝の関係は良好ではなかったようで、2人が協力することはありませんでした。
治承・寿永の乱 解説⑤
南都焼き討ち(1180年)
全国各地が反平家ムードに包まれる中、園城寺や興福寺といった寺社勢力の蜂起も促されます。



この頃は武装した僧(僧兵)がたくさんいたね!!
しかし、落ち目であるとはいえ、平氏は戦のエリート集団。園城寺の鎮圧に成功します。
その後、平清盛の命を受けた平 重衡 が、大軍を率いて興福寺(南都)に向かいます。



平清盛は穏便に事を済まそうと興福寺側に使者を送るんだ。けれども南都側は使者を捕らえて斬首。清盛を激怒させたよ。
興福寺側が築いた柵や堀を、大軍で突破。
そして、放火によって興福寺や東大寺を焼いてしまいました。
これが南都焼き討ちです。
この火事によって多くの人が焼死。平氏への恨みがますます強くなります。
(南都焼き討ちに関しては、重衡の予想を上回るものだった、計画的なものだった )という二つの説があります。



ちなみに南都は興福寺、北嶺は延暦寺だったね!!
治承・寿永の乱 解説⑥
平清盛の死(1181年)
南都焼き討ちが終了したころ、清盛は病に倒れ、高熱にかかります。



清盛に水をかけると、あまりの高温で水がお湯になったらしいよ!!
それから清盛は突然の死を迎えます。このことから、清盛は南都を焼き討ちにした罰が当たったのだと噂されるようになります。
治承・寿永の乱 解説⑦
平家の都落ち(1183年)
清盛の死後、平家は急速に勢力を失います。
連敗に次ぐ連敗で、反平家軍の侵攻を止める力を失い、ついに京を離れる決断をします。
平家棟梁・平宗盛は、幼い安徳天皇と後白河法皇を引き込連れて一旦西国に逃走することを計画。
ところが、平家の動きを素早く察知した後白河法皇は、密かに比叡山へと逃げ込みます。



比叡山に籠られてしまうと、僧兵の妨害によって、後白河法皇を連れ戻すことができないよ。
後白河法皇を取り逃してしまった平家は仕方なく、権威を保つための三種の神器と安徳天皇を連れて、京を去ることになります。
治承・寿永の乱 解説⑧
木曽義仲の都入り(1183年)
平家が都落ちしたことで、木曽義仲が入京します。
しかしこの頃、平安京では飢饉が発生しており、大量の人々を賄える余裕はありませんでした。
義仲の軍勢は盗賊行為を繰り返すようになり、都の厄介者として扱われることになります。



京の厄介者となってしまった木曽義仲。彼を追い出す役目に抜擢されたのが源頼朝だよ!!
治承・寿永の乱 解説⑨
寿永二年十月宣旨(1183年)
幽閉生活から解放された後白河法皇は、再び院政を始めます。
しかし、一度崩れた体制を整えるために、どうしても解決しておきたい問題が2つ。
危険因子である平家の滅亡と厄介者の木曽義仲の排除です。



この2つの問題解決に、源頼朝が抜擢されるよ。
しかし、頼朝もただでは動きません。
・自分の身分を元に戻すこと
・東国(東海道・東山道)の支配権を与えること
上記2つを要求します。



頼朝は保元の乱で負けた源義朝の息子。命は奪われなかったけど、罪人として処理され、身分を大きく落としたよ。
頼朝の要求を後白河法皇は承諾。
寿永二年十月 に、頼朝に東海道、東山道の支配権を与える 宣旨 を出します。



この東国支配権が、後に鎌倉幕府を置く布石になるよ!!
頼朝は源義経と源範頼に平家と木曽義仲の討伐を命令。歴史を大きく動かす戦いがスタートします。
治承・寿永の乱 解説⑨
宇治川の戦い(1184年)
連戦連勝だった木曽義仲軍ですが、平家が得意とする海上での戦い 『水島の戦い』で敗北してしまいます。



敗戦の知らせはすぐに、木曽義仲のもとに届いたよ。
戦いの勝利によって、平家に勢いがつくのはマズいと判断したのか、木曽義仲は平家討伐の準備を始めます。
しかし戦の準備をしている最中に、義仲は『自分を倒すための命令』が下されたことを知り、急遽、平安京へ戻ります。



当然、義仲はものすごく怒っているよ!!
義仲は法皇の院御所である法住寺殿を襲撃。後白河院を捕らえ、幽閉します。



平治の乱、治承三年の政変に続く後白河法皇の人生3度目の幽閉だよ。
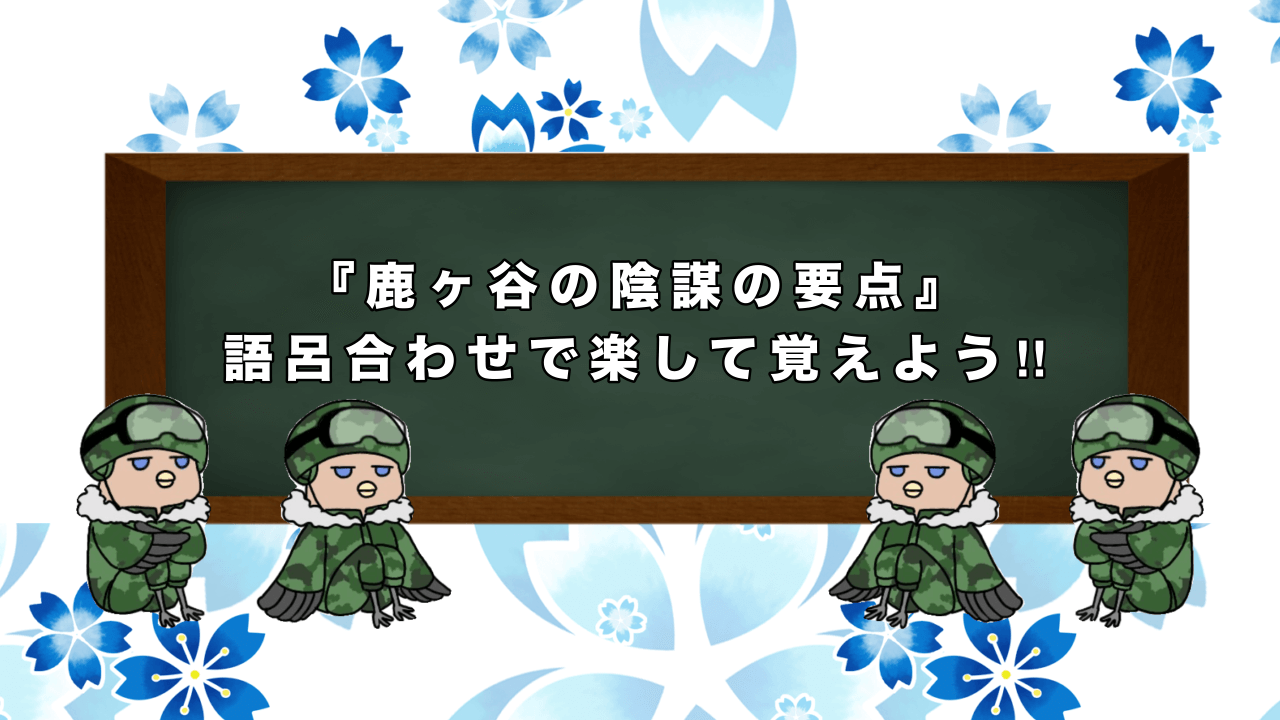
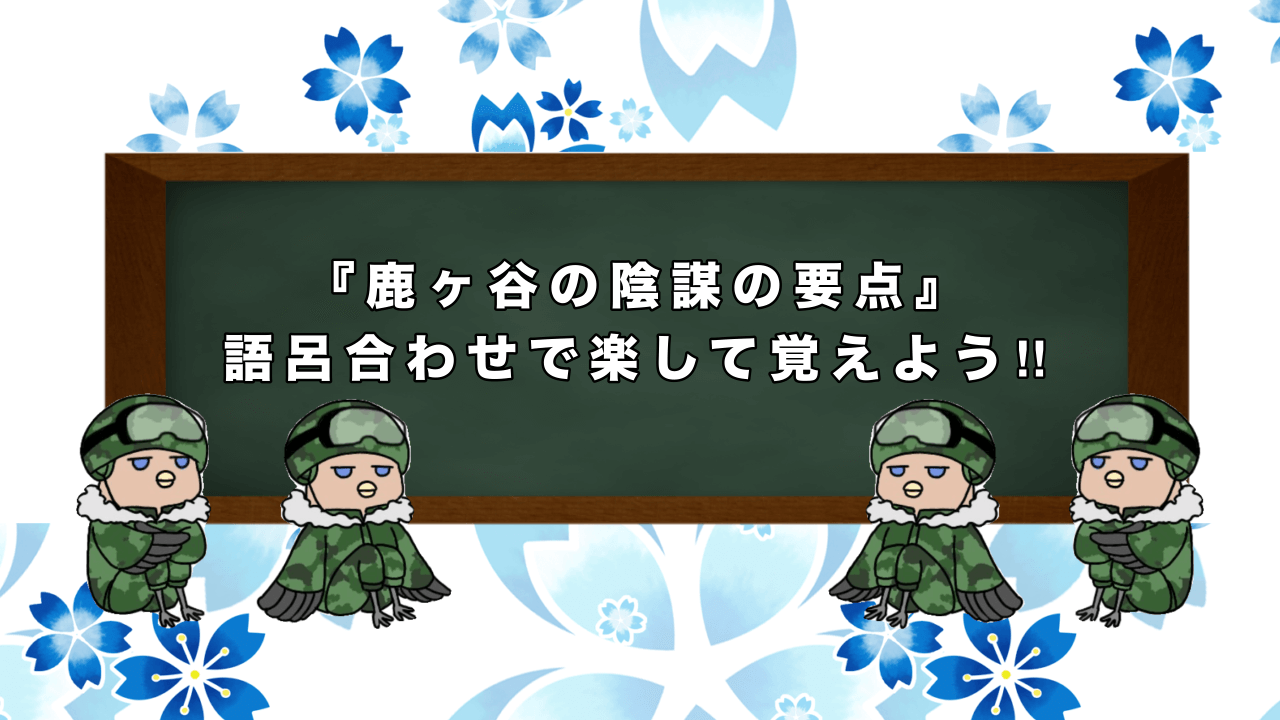
しかし、1184年、宇治川の戦いにて、源頼朝に派遣された源範頼・義経軍によって木曽義仲は敗死。
波乱万丈な人生に幕を下ろしました。
治承・寿永の乱 解説⑩
一之谷の戦い(1184年)
源氏と木曽義仲が互いの勢力を削り合っている中、平氏は勢力を盛り返し、一之谷(現在の兵庫県付近)に城を構えていました。
木曽義仲討伐後、後白河天皇は義経と範頼に平氏の追討と三種の神器の奪還を命令。
こうして一ノ谷を舞台に、戦いが始まりました。



一之谷は山々に囲まれて入り口も少ない天然の要塞。そう簡単に攻略できないよ!!
しかし、義経は奇策使い、難攻不落の要塞を突破します。
それが馬に乗って崖を一気に降る戦法です。鵯越の逆落としと呼ばれています。
この戦法によって平氏軍は大混乱。屋島へと敗走します。
治承・寿永の乱 解説⑪
屋島の戦い(1184年)
屋島は現在の香川県 高松市付近に存在しました。



当時はまだ陸続きじゃなかったから、屋島に攻め入るには、船とそれを動かす水夫が必要だったよ。
源氏軍は、船も水夫も持ち合わせていなかったので、一之谷の戦いで勝利した勢いで屋島に攻め入ることはできませんでした。
源氏軍として派遣されていた源範頼・源義経は、一度撤退。
戦が再開した際、はじめは範頼だけで平家追討を行いましたが、予想以上に時間がかかり、後に義経も参戦。
義経は四国に上陸し、屋島攻略の情報を集めながら平家側の武士と戦います。
そして屋島攻略の際は、大軍に見せる策を活用し、少数で攻め落とすことに成功します。
治承・寿永の乱 解説⑫
壇ノ浦の戦い(1185年)
一ノ谷と屋島の戦いで敗北し、後に引けなくなった平氏軍は壇ノ浦で源氏軍と最終決戦に挑みます。



海上での戦いを得意とする平氏軍。潮の流れも平家側に有利で、最初は源氏軍を圧倒していたよ。
しかし、時が流れるにつれて潮の流れが逆転。源氏が有利な方向に変わります。
さらに、義経軍は平家軍の船の漕ぎ手に向かって集中して矢を発射。
平家の漕ぎ手は次々にやられ、平家軍の勝ち目は限りなく薄く……。
「もはやこれまで」と感じた平家側の人間は次々と海に身を投げます。



さらに安徳天皇も母に抱えられ一緒に入水。
短い人生に終わりを告げるよ。
以仁王の令旨から5年の歳月を経て、平家は滅亡。源氏が時代の覇者として君臨することになります。
便利な語呂合わせ 治承・寿永の乱の覚え方
平家滅亡に至るまで、様々な出来事が
立て続けに起こる治承・寿永の乱。そのため
出来事の順番が分からなくなる。
覚える量が多すぎて覚えきれない。
上記のようになる人、いると思います。



そこで便利な語呂合わせを考えたよ!!
出来るだけ無理やり感なく覚えやすいように作ったから暗記にぜひ役立ててね!!
便利な語呂合わせ①
1180年に起こった出来事
以仁王の令旨 福原京遷都 木曽義仲の挙兵……
と多くの出来事が起こっている1080年。



簡単にかつ一気にまとめて覚えたいね!!
そんなときは、下記のように覚えましょう!!
餅をたらふく 吐きそうなんて 言い張れない
餅…以仁王の令旨
餅から以仁王を連想
たらふく…福原京遷都
たらふくから福原京を連想
吐きそう…木曽義仲の挙兵
吐『きそ』う → 木曽
なんて…南都焼き討ち
なんて から 南都 を連想
言い張れない…1180年
言い張れ
便利な語呂合わせ②
清盛の死 1181年
治承・寿永の乱のターニングポイントになった
平清盛の死も語呂合わせで覚えましょう!!
語呂合わせは
清盛の死は 源氏にとって 祝 い の日



ちょっと無理やりだけど、何度も唱えてたら、
自然と暗記できるようになるよ!!
便利な語呂合わせ③
平家の都落ち から 壇ノ浦の戦いまで
平家の都落ち から 壇ノ浦の戦いまで
の語呂合わせは、
平気そうだから今日中に 嫌~な仕事 頼んだよ
平気そう……平家の都落ち&木曽義仲の都入り
今日中に……寿永二年十月宣旨&宇治川の戦い
『中に』から 『二年十月』と『宇治川』を連想
嫌~な……一之谷の戦い&屋島の戦い
『嫌』から『一之谷』と『屋島』を連想
頼んだよ……壇ノ浦の戦い



紹介した3つの語呂合わせを覚えれば、
治承・寿永の乱の流れは完璧だよ!!
終わりの言葉
勉強、お疲れさまでした!!
治承・寿永の乱の流れは、並べ替え問題でも頻出です。
だからこそ、しっかりと押さえておくことで、周囲との差をさらに広げることができます!!
引き続き、当ブログでは高校日本史の語句や出来事の簡単な暗記法や語呂合わせを記載していきます。



このブログを見たおかげで問題が解けた!! 暗記が楽になった!!
といった感想を持っていただけると嬉しいよ!!
効率よく時間をかけずに出来事を暗記したい!!
という方は、ぜひ他のページもご覧になってください!!